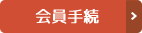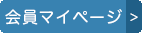1.これまでに学会にいただいた質問
○認定施設での研修、カリキュラム受験資格や認定試験、専門医更新に関する Q&A
ここに掲載するQ&Aは、実際に寄せられた問い合わせの多い質問とそれに対する回答をアレンジして掲載しています。
その他、質問がありましたら学会にお問合せください。
4.指導医について
1.研修制度全般について
Q1-1:臨床検査専門医の資格取得について、基本的なことから知りたいので、本件に関するメールや電話での相談窓口を教えてください。
Q1-2:プログラム制とは?
Q1-3:カリキュラム制とは?
Q1-5:基本領域は既に内科専門医を持っており、臨床検査専門医の取得を検討しております。
Q1-6:すでに総合内科専門医およびサブスペシャルティの専門医を有している医師が、日本専門医機構の臨床検査専門医を目指すにはどのようにすべきでしょうか。
Q1-7:臨床検査部長ならびに病理解剖医として当院に勤務しており、臨床検査専門医資格の取得を強く希望しております。
Q1-8:202X年4月より検査部に赴任しました。臨床検査医を目指したいと考えていますが、プログラムの受付は終了したと伺っているのですが、今年度途中から専門医プログラムへの参加は可能でしょうか。
Q1-9:自分はカリキュラム制での研修になると思いますが、過去にさかのぼって研修を開始していた旨の手続きは可能でしょうか?
Q1-12:カリキュラム制の研修について、3年間で計36単位は、特に各1年間に必ず12単位という形でなくても良いのでしょうか。3年間で合わせて計36単位という認識でよろしいでしょうか?
Q1-14:「連携施設」という名称とは別に、「関連施設」がありますが、どういう施設でしょうか?(指導医から)
Q1-15:まだ開院して間もない病院ですが、連携施設基準に合致するかどうかを検討し、申請を挙げるという流れでよいでしょうか?(指導医から)
2.研修実績・修了時提出資料について
Q2-1:専攻医が修了認定を受けるために提出すべき書類についてご教示いただけますと幸いです。
Q2-2:報告書は「各基本科目を最低1通含み計36通以上作成する」とあります。基本科目とは何でしょうか?
Q2-4:「4. 研修修了判定と提出書類」で、「プログラム統括責任者は学会委員会に、様式 F2、様式 F3、修了認定をした際の研修プログラム管理委員会の議事録を提出してください。」と書かれています。一方で、実施要領(2024 年度:例) の「日本専門医機構 認定 臨床検査専門医研修修了書類提出及び第 4 回認定試験実施要領(2024 年度)」には、専攻医の提出書類として「臨床検査専門医 専門研修修了 通知書(様式 F2)」「臨床検査専門医 専門研修修了 確認書(様式 F3)」が挙げられています。
様式 F2 と様式 F3 の書類は、プログラム統括責任者から学会に提出するのか、専攻医から学会に提出するのか、あるいは両方なのか(同じ書類をプログラム統括責任者と専攻医の双方から提出するのか)、どうすればよろしいでしょうか? また、「修了認定をした際の研修プログラム管理委員会の議事録」は、専攻医には渡さず、プログラム統括責任者から学会委員会に提出するべきものでしょうか? また、プログラム統括責任者からこれらの書類を提出する際は、郵送でもメールでもよいのでしょうか?
Q2-5:「報告書の作成とコンサルテーションへの対応」で、検査報告システム上、判読またはコメント作成に関わった専攻医の名前を報告書に残せない場合の対応はどうしたらよいでしょう?
Q2-7:「報告書の作成とコンサルテーションへの対応」で、アイソザイムや免疫電気泳動を院内で行っていない場合はどうしたらよいでしょうか?
Q2-8:「報告書の作成とコンサルテーションへの対応」で、個人情報への配慮はどうすればよいでしょうか?
Q2-10:レポートやその他の記録書については、デフォルトがあるでしょうか?
Q2-13:RCPCを受講し記録を提出とあります。提出する記録とはどの程度の記載が必要でしょうか?
Q2-14:RCPCを9回(自施設例によるものを最低3例含める)受講するとなっています。RCPCの規模や行われる施設について教えてください。
Q2-15:プログラム研修で、RCPCを計画しておりますが、この部分の個人情報はどのように対応すればよろしいのでしょうか?
Q2-16:研修実績記録と研修評価表で、表の空欄には日付を入力すればよいのでしょうか?また年度ごとの記載か、3年間まとめての記載でしょうか?A〜Eまでの評価基準の根拠と求められるレベルはどのようなものでしょうか?
Q2-17:自己レポートはどの程度のレベルが求められるでしょうか?自身の担当症例ではなくカルテ調査等でも可能でしょうか?
Q2-18:チーム医療活動、RCPC、地域医療への参加はどのような提出資料が求められるでしょうか?
Q2-19:地域医療の経験について教えてください。
Q2-21:地域内における種々団体が開催する臨床検査の啓発事業への参加というと、どのようなものが具体的に挙げられるでしょうか?
Q2-22:OSCEの外部評価者に協力した場合、地域への貢献として単位が認められるでしょうか?
Q2-25:外部精度管理の資料として、外部精度管理調査書(地域や技師会などが調査結果を病院に報告したもの)に専攻医の名前を追記したものでもよいでしょうか?
Q2-26:専門医更新の際の診療実績(内部精度管理の書類)について、提出予定の当院使用中の書類をご確認いただけますでしょうか??
Q2-29:原著論文や症例発表に関して、他の学術集会での筆頭症例発表、またその発表をその学会機関誌 にて筆頭著書で報告した場合は、専門医受験資格の筆頭演者の発表や学会報告として認められるのでしょうか。
Q2-30:学術活動で、「臨床検査医学(臨床病理学)に関する筆頭者としての原著論文が1編」とありますが、生理学(心臓超音波検査)の論文も該当論文としてカウントされると考えてよろしいでしょうか?
Q2-31:結婚により苗字の変更(登録時の旧姓)があり、日本専門医機構のJMSB Online System+ 上の変更に手間取っています。
Q2-32:専門医機構のシステム上での操作について、専攻医のページ上で「研修修了申請」を行い、プログラム統括責任者のページ上でその確認をしていただく、という流れでよろしいでしょうか?
3.研修中の問題について
Q3-2:現在、症例報告の論文を作成し、和文医学雑誌に投稿しようと考えているのですが、これは実績として認められるでしょうか?
Q3-4:雑誌に投稿した症例を学会でも発表したいと考えているのですが、各々1症例としてカウントすることは可能でしょうか?
Q3-5:カリキュラム制の専攻医なのですが、「他施設での地域研修」は必要でしょうか?
Q3-6:現在、他院の専門医研修プログラムで研修中(2年目)の医師が諸般の事情により、当院のプログラムに転籍して研修を継続することは可能でしょうか?(指導医から)
Q3-8:当院は基幹施設ですが、来年度から連携施設維持が困難であり連携解消となりそうです。今後、臨床検査の専門医研修についてはどうすればいいのか、大変困った事態になりました。(指導医から)
Q3-10:専門医取得プログラム(A病院主幹)に入ったあと、他のプログラム(B病院主幹)に変更することができますでしょうか。
Q3-13:来月より連携病院にて2ヶ月ほど専攻医研修を受けることとなりました。学会として、連携施設での研修修了証についてフォーマットなどあるでしょうか?
4.指導医について
Q4-1:日本専門医機構 認定 臨床検査専門医の指導医とは?
Q4-3:研修プログラム管理委員および指導医は、今年専門医取得予定の者も含めて良いでしょうか?
Q4-4:専門医の自分が異動予定です。プログラムを維持するためには、専門医を持っていない後任の医師が統括責任者となり、指導のメンバーに専門医の医師が所属しているという形でもよいでしょうか?(指導医から)
5.産休、育児休暇について
Q5-1:専攻医が、来年の春頃まで、出産、育児のため、研修をお休みします。この場合、どういった届けを、どこに提出したら、よろしいですか?(指導医から)
Q5-4:現在はプログラム制にて研修中ですが、出産・育児のため今後プログラム制での研修が難しく、カリキュラム制へ移行を考えています。
6.研修の辞退について
Q6-1:大学病院にて臨床検査専門医研修中(カリキュラム制)、他施設に異動することになりました。そのため研修を中断、中止しなければいけないと考えておりますが、どのようにしたらよろしいでしょうか?
Q6-3:大学退職に伴って、研修を終了するつもりです。プログラムの辞退の申請方法は?
7.専門医更新について
Q7-1:診療実績で、サイン(自著)が発生しない場合はどうしたらいいでしょうか?例えば、電子カルテでかつサイン欄がない場合や会議の出席記録など。
Q7-2:診療実績の証明(必須)は一種類でいいでしょうか? あるいは、報告書3系統以上必要なのでしょうか? あるいは、診断報告書、検査部門管理記録、コンサルテーション記録「等」と言うことでしょうか?
Q7-3:更新時に必要な日常業務での報告書は、異動した場合などは、認定研修施設でない施設での報告書でもよいでしょうか?更新料も教えていただけると助かります。
Q7-5:資格更新を延長している期間中に満65歳を迎えた場合でも、特別基準2が適用され、診療実績が免除+40単位で更新する方法を選択できますか?
Q7-6:学会専門医での更新申請はできますか?
Q7-7:専門医更新時に向けた単位取得の開始日は毎年の1月1日からでよろしいのでしょうか?
Q7-9:学会講演の内容が後日e-learningで受けられる場合、1日の受講限界単位はe-learning分は適応外でしょうか?
Q7-10:3日間の学術集会でのオンデマンドでの受講の場合、取得可能な単位は10単位までとなっていますが、オンデマンドですべてのもの(10単位以上になる場合)を1日に受講した場合は、単位として認められるのですか?
Q7-12:共通講習の取得単位は他の基本領域の機構専門医(例えば内科専門医)で再利用出来るのでしょうか?
Q7-13:以前リウマチ学会総会で共通講習(感染症、倫理、安全対策)を受けました。 こちらは5年以内であれば専門医更新の単位として認められるでしょうか。
Q7-16:「2027年4月1日更新以降の日本専門医機構臨床検査専門医更新基準のポイント」について質問です。
参考: 更新について > [2023/07/24]2027年4月1日付以降の日本専門医機構 認定 臨床検査専門医更新基準(日本専門医機構2023/07/21承認)
> 改訂のポイントについて
多様な地域における診療実績が認定された場合は必修項目 B免除されるとあります。 【臨床検査領域では、この診療を、「臨床検査医師が10人に満たない都道府県でかつ大学病院以外で勤務した場合」と定義しています。この実績を満たすことは現実的に困難なことが予想されます。その場合は「ベテランのエキスパートと同様に必須修講習Bを受講してください。】 とあります。
①「臨床検査医師が10人に満たない」とあるが、これはどの時点で10人に判断されるのか更新年度ですか?更新までの5年間の平均ですか?
② 自分の県に10人の医師がいるかどうかどのように調べればいいですか? 簡単に県の臨床検査医師のリストを調べられるシステムはウェブ上にありますか?とりあえず、学会に質問して教えてもらえますか?
2. 【入門編】臨床検査医学と 臨床検査専門医について
Q3:臨床検査専門医のトップの方はどのような仕事をしているのでしょうか?
Q4:臨床検査医学講座と中央臨床検査部との関係はどうなっていますか?
3. 専門医取得 対象者別ガイド
○臨床検査専門医を目指す方へ 【2024/10/17 更新】